目次
第1章:DX=IT導入じゃない。「やり方」と「考え方」を変えること
「うちもDXを始めたほうがいいのかな?」
そんな相談を、最近よく受けるようになってきました。
たしかに「DX(デジタルトランスフォーメーション)」という言葉はよく耳にします。でも、多くの方が口をそろえて言うのが、「結局、何をすればいいのか分からない」という言葉です。
実際、DXとは「パソコンを新しくすること」でも、「AIで何かすごいことをする」ことでもありません。
国の『DX推進の手引き2025』では、DXを以下のように説明しています:
顧客視点で新たな価値を生み出すために、ビジネスモデルや企業文化を変革すること。デジタル技術を活用することが目的ではなく、それを手段として経営のあり方そのものを見直すこと。
つまり、DXの出発点はこうです:
- 「どうやって仕事をしているか」
- 「誰のためにやっているか」
この問い直しこそが、DXの本質です。

たとえば、これまで手書きだった注文票をエクセルに変えただけでは「デジタル化」止まり。しかし、それがスタッフ全員で共有され、「今日の在庫は大丈夫そう」と判断できるようになれば?
それは、行動が変わったということ。つまり、DXが始まった証です。
ありがちな失敗は、「ツールを入れれば自動的に変わる」と思い込むこと。
どんなに高性能なシステムも、「何を変えたいのか」が明確でなければ、宝の持ち腐れです。
一方で、「毎月3時間かかっていた集計作業を1時間にしたい」「スタッフ全員が予定を見えるようにしたい」といった小さな困りごとからスタートすれば、無料のアプリでも十分に効果が出ます。
そして何より大切なのは、最初に変わるべきは現場ではなく、経営者自身だということです。DXの出発は、経営者がリーダーシップを持つこと。ツールの使い方を覚える必要はありません。詳しい人材がいなくても問題ありません。 大切なのは、「5年後、自社をどうしていきたいのか」という問いに、正面から向き合う姿勢です。
第2章:「最初の一歩」でつまずかないための視点──まず現在地を知る
「DXの必要性は分かった。けれど、何から手をつければいいのか分からない」
これは多くの中小企業の経営者が抱える、共通の悩みです。
ここで焦ってツールを導入してしまうと、「使いこなせずに終わった」「かえって現場が混乱した」など、もったいない結果になってしまいます。 まず大事なのは、自社の現在地を正しく把握すること。つまり、DXの前に現状の棚卸しが必要です。

次のような視点から、自社を振り返ってみてください:
- 毎月の売上・利益をリアルタイムで把握できているか?
- 誰かが休んでも業務が回る仕組みになっているか?
- 顧客情報や在庫が紙や担当者の頭の中だけに偏っていないか?
一つでも不安があれば、そこがスタートラインです。
成果を出している企業の多くは、帳票をクラウド化する、勤怠をオンラインで共有するといった「シンプルで身近なこと」からはじめています。
そして「これ、便利だね」「ラクになったね」という小さな成功体験が、社内に前向きな空気をつくります。ここが変化の原動力になります。
そのためには、「現状を一緒に整理してくれる相手」が必要です。たとえば、よろず支援拠点や専門家の伴走支援がその役割を担います。
DXとは、遠い未来の話ではなく、「いま抱えている困りごと」を出発点にできる経営改善の手段です。
第3章:DXの4つの誤解──よくある遠回りを避けよう
実際の現場で、DXの取り組みがうまくいかない原因の多くは「思い込み」です。ここでは、よくある誤解を4つ紹介します。
誤解①:「補助金でシステムを入れれば、DXになる」
→ 補助金で立派なシステムを入れても、現場で使われなければ意味がありません。大切なのは「導入」より「運用し、成果を出すこと」。
誤解②:「若手に任せておけば、なんとかなる」
→ 「若い人が詳しいから」と任せっきりにすると、現場と経営が分断されます。DXは経営の意思決定と連動してこそ機能します。
誤解③:「AIやRPAを入れれば、一気に効率化できる」
→ ツールはあくまで手段。業務の流れや目的が整理されていなければ、宝の持ち腐れになります。まずは足元から整えるのが正攻法。
誤解④:「社内でなんとかしなきゃいけない」 → 「外部に相談するのは大げさ」と感じるかもしれませんが、うまくいっている企業ほど支援機関や外部専門家を上手に使っています。
第4章:「ちょうどいいDX」の始め方──大きく始めず、小さく動かす
「DX」と聞くと、大掛かりな改革を思い浮かべてしまいがちですが、実際には今できることを一つだけ変えるのが最初の一歩です。
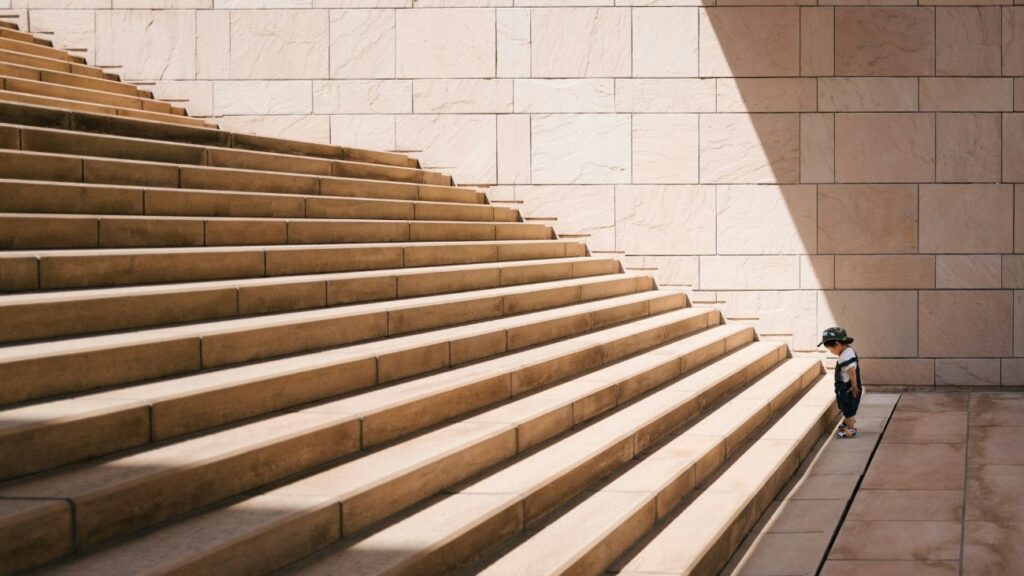
たとえば:
- 紙で管理していた予定表を、Googleカレンダーにしてみる
- メールでのやりとりを、ChatworkやLINE WORKSに変えてみる
そんなほんの少しの工夫が、スタッフの働き方や情報の流れを変えるきっかけになります。
そして、「便利になった」「助かった」という声が生まれれば、それが次の変化の種になります。
完璧な計画も、高額なシステムもいりません。
「今すぐ変えられそうな、たったひとつのこと」から動き出すこと。それがちょうどいいDXの始め方です。
第5章:私たち支援者ができること──答えではなく、問いを一緒に探す
DXは「技術の話」ではありません。「人と組織が、どう変わっていくか」という話です。だからこそ、「誰かと一緒に考えること」が欠かせません。
『DX推進の手引き2025』では、支援者の役割として「経営者に気づきを与える壁打ち相手であること」が強調されています。私たち支援者にできるのは、話を聞き、言葉になっていない課題を整理し、「何がボトルネックなのか」「何を変えたいのか」を経営者と一緒に見つけることです。 答えを押しつけるのではなく、問いを一緒に考える。進むペースに合わせて並んで歩く。それが「伴走支援」であると考えています。
第6章:まとめ──DXとは「変わり続ける力」
DXとは、単にツールを導入することではありません。
変わり続ける力を、会社の中に根付かせること。
「本当にこのやり方でいいのか?」と問い直し、
身近なところから少しずつ、無理なく、変えていく。
その繰り返しが、企業文化や働き方をじわじわと変えていきます。 私たち支援者は、そのはじまりを一緒に支えます。地域に根ざし、経営者の思いや悩みに寄り添いながら、地域とともに、一歩ずつ変わっていける未来を目指します。
栃木県よろず支援拠点では、ちょっとした不安ごとから深刻なお悩みまで、経営に関するご相談を経験豊かな専門家が無料でお応えいたします。
まずは下記「無料相談予約」ボタンよりご予約ください。

これから創業をお考えの方のご相談もお受けしています。
たくさん考えることがありすぎて、漠然とした不安を抱えていらっしゃる方もお話しいただくことでやるべきことが整理されることもあります。ぜひ、お気軽にご相談ください。